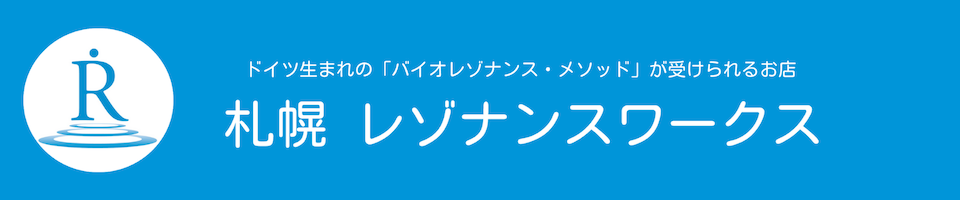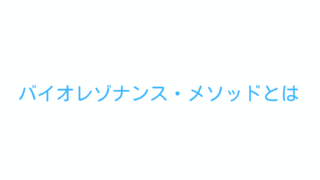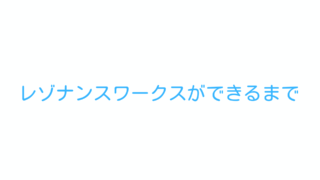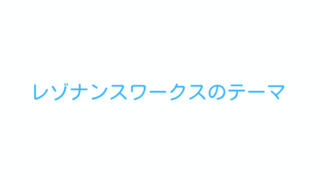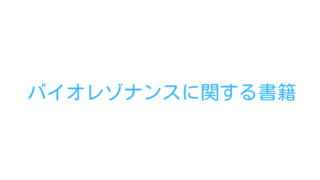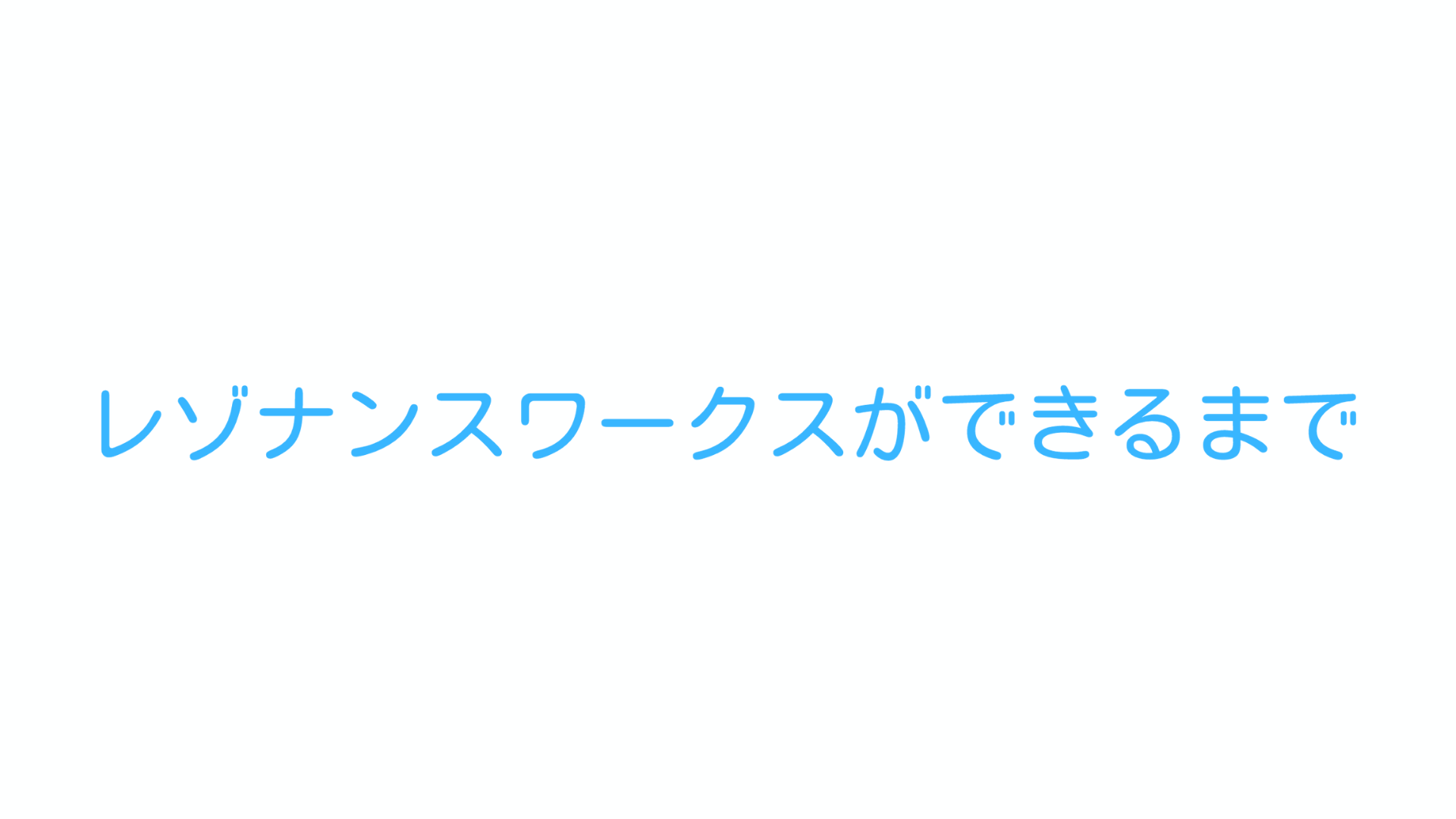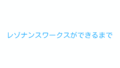第2期 整体学校時代(1998年〜1999年のころ)
ここでは、その後の自分に影響があった授業内容などが記されています。
ひとつひとつのパーツが時間を経て徐々につながっていったんだなぁと改めて思いました。
ユニークな授業
わたしが通った整体の学校では解剖学などの座学や筋肉や関節を緩めるといった一般的な実技を学ぶ一方、ユニークな授業もありました。
わたしがおぼえているのは次の2つ。
いずれも実技の先生からの提案でした。
音楽を聴く授業
- 「聴くと元気が出る曲」
- 「悲しい時に聴く曲」
- 「楽しい時に聴く曲」
生徒各自にこの3種類の曲を持ち寄らせて、誰が選んだのかは伏せたまま順番に聴かせるという授業がありました。
生徒が持ち寄った曲を聴きながら、「へぇ〜!悲しい時にこの曲を聴くんだ!」とか、「これを聴くと元気になるんだね!」など反応は様々。
同じテーマでも人が違えばこれだけ選曲に違いがある。
同じように「感じること」にもそれぞれ個性があるので、そこを意識しながら施術ができるようにと教わりました。
つらい場所にただ触れる
相手がつらいという場所に圧力は一切加えず、手のひらでただ触れるという授業もありました。
2回に分けて触れるのですが、そのときの条件として、
- 「何も考えないまま手を触れる」
- 「良くなれと考えながら手を触れる」
このうちのどちらをやっているのか、相手に伝えずにというのがありました。
わたしは最初触れられたとき、ズキズキとうずいて滅茶苦茶痛くなりました。
「悪くなれと思って触っているんじゃないだろうか?」
と思ってしまうくらい痛かったのをおぼえています。
2回めの時は全く何も感じずに、「あぁ、手を置かれているな」と思った程度でした。
答え合わせをすると、最初が良くなれと思い、2回めは特に何も考えなかったそうです。
それを聞いて、当時、日常的につらかった肩甲骨付近が「良くなれ」という思いで触れられることによって、通りが良くなり、滞りが解消して流れが出来ていったための痛みだったのかなと思いました。
このことで施術する側がどのような気持ちでいるのかが、相手にも充分に伝わるということを実感しました。
たとえ相手がそれを感じとれなくても、同様の影響をその身体に与えているとわたしは考えています。
氣功の授業
学校には氣功をメインに教えてくれる先生もいて、週一回の授業では呼吸法をメインに教わりました。
背骨を意識して、呼気と吸気がそこを行ったり来たりするようにとか、右手から左手に反時計回りで”氣”をめぐらせるなど。
授業が進むにつれて、先生が普段おこなっている技術も学びました。
親指の指先で患部をピンポイントで捉えて、そこに一気に”氣”を送って痛みを軽減させるという方法です。
先生は「患部を一瞬で射抜く感じで」と表現されていました。
ただ先生と学生とのレベルが違いすぎて、あくまでもこのような方法だよと教わるだけで、その技術を再現することは誰にも出来ませんでした。
実際に受けてみて
わたしは入学前から左足のふくらはぎが、常に重くだるい状態が続いていました。
朝起きるとまずはふくらはぎのストレッチからスタートという日々でした。
この先生の施術がいったいどのようなものなのかを知る良い機会だと思い、お願いして授業中に受けさせてもらいました。
先生がわたしのふくらはぎに指を置いて、「じゃぁ、やるよ!」と言われた瞬間、「ドン!」「ドン!」と2ヶ所に激痛。
「はい、立って。」と言われて立ち上がってみると、強く圧迫された痛みはあるものの、不快さは激減。
「うわっ!なんだこれ!不思議だわ〜!」
これ以来、朝起きてのストレッチの必要はなくなりました。
実験台はたいへん!
このポイントの捉え方を学ぶにあたって、実験台になるのは大変なこと。
滅茶苦茶痛いからです。
先生が実際におこなう施術はいつも一瞬のことなのですが、捉える方法を学生たちに教えるためには長い時間ポイントを押さえながら、角度や強さの説明が必要になってきます。
その間、受け手はずっと痛い思いをするわけです。
同期が実験台になっていたある時のこと、こんなことがありました。
あまりに「痛い、痛い」と言っているので、わたしが調子の乗って、
「先生、こいつに今までで一番恥ずかしかったことを白状させましょうか?」とか、
「おい、痛い思いから開放されたかったら、一番恥ずかしかったことを言え!」
などとからかったりしていました。
すると彼が痛みに耐えながら
「買ったばかりの新車を壁にぶつけた日に、彼女に振られましたぁ!その日は雨でしたぁ!」
と白状。
ただそれは彼の話ではなく、わたしの話。
「バカヤロウ、それ、俺の話じゃないか!一昨日、居酒屋で飲んだ時に話したことでしょうが!」と
みんなは大笑い。
「レゾナンスワークスができるまで」を書きながら、懐かしい話を思い出しました!
チャクラの話
ある日の休憩時間、実技の先生と話をしていたときのこと。
その先生が
「チャクラというのがあって、それぞれ色があるんだよね。」
といった内容の話をしてくれました。
今でこそ、ヨガやスピリチュアルの話題も増えてきましたので、「チャクラ」という言葉を耳にされた方も多いと思います。
しかし当時(1998〜1999年頃)はまだそれほど一般的ではなかったはずで、わたしも「チャクラ」という言葉は初耳でした。
調べてみると、チャクラは7つあって、それぞれに「色」もあるし「音」もあるみたいなことが書かれていました。
色に関しては第1チャクラは「赤」、第2チャクラは「オレンジ」など。
音に関しては第1チャクラから第7チャクラに向けて順番に「ドレミファソラシ」と音階が上がっていくなど。
「チャクラごとに音があるんなら、臓器ごとにも音があるんじゃないだろうか?」
と当時漠然と思ったのをおぼえています。
このことが後に記す整体院での体験に結びついていくのです。
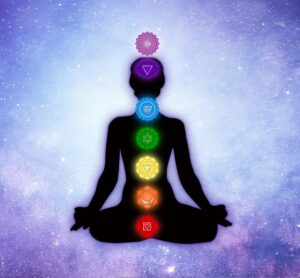
中学生の頃
この「色」に関しての話は中学生の頃に遡ります。
当時住んでいた家の話です。
自分の部屋はあまりにも寒くて、冬の夜など足先が痛くてなかなか寝付けないことが多く困っていました。
北向きの部屋で、日中もほとんど日が入らないような環境でした。
中学生だったある冬の日。
その晩も寒くて、足が痛くて寝付けません。
なにか解決策を考えないと、このままではどうにもならんという状況でした。
眠れないまま、ふと
「”赤”とか”オレンジ”とか暖かい感じの色で足を包んでみたらどうだろう?」
「もしかしたら暖かくなるんじゃないだろうか?」
などの考えが浮かび、足首から先が赤い色で包まれているというイメージをしてみました。
するとしばらくして足先がポカポカとしてきたのです。
「これは便利だ!」と思い、以来、寒いときは足先だけでなく手や背中など、からだの色々な場所を望む色で包むようになりました。
暑い時などは逆に涼しく感じる水色でなどで。
やりなれてくるうちにイメージもバージョンアップして、足や腕を一本のパイプ管のように見立てて、その中を赤やオレンジ色の空気を行ったり来たりさせながら身体を暖められるようにまでなりました。
じつは普通のことではなかった
このことは誰もが普通にやっていることだと思っていましたので、特に誰かに話しをするわけでもなく、あまり気にもとめていませんでした。
片手にお箸を持って、もう片方でご飯茶碗を持ってご飯を食べるといった、みんなもやっているごく普通の出来事のように考えていたのです。
しばらく経った会社員時代のあるとき、先輩が「夜が寒くて寝られないんだよなぁ」と言っているのを聞いて、わたしがやっていることを何でやらないのか、不思議な気持ちでそのまま伝えました。
すると「おまえ、何言ってんの!そんなことできるわけないじゃん!」
このとき初めて、自分がやっていることが普通の事ではないんだと気づきました。
それから10数年経ってから、このテクニックが「カラーブリージング」というものらしいということを知りました。
前もってこのような体験をしていましたので、整体学校を選ぶときに「氣功の授業」があるというのは大きな決め手となったのです。